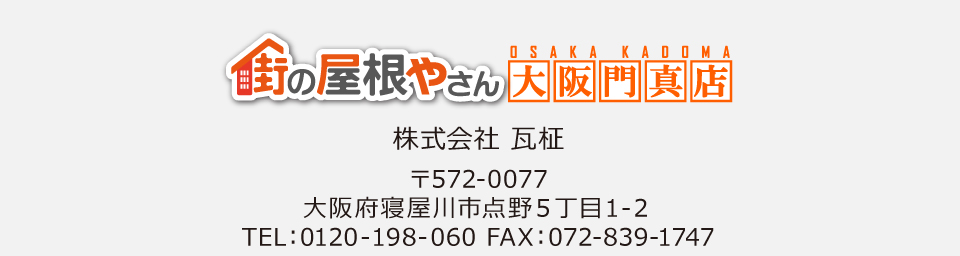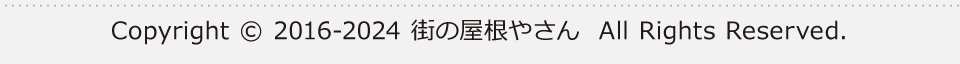2025.12.23
寝屋川市の蔵の屋根を見て欲しいとのご依頼を頂きましたので、現地調査に伺いました。昔ながらの大きな家にはこのような蔵がある家が良く見られます。【蔵】とはどんな建物なのか? 蔵は、古くから日本の暮らしを支えてきた伝統的な建物です。大切な家財や食料などを収納するために建てられました。 …







街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん大阪門真店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2025 街の屋根やさん All Rights Reserved.